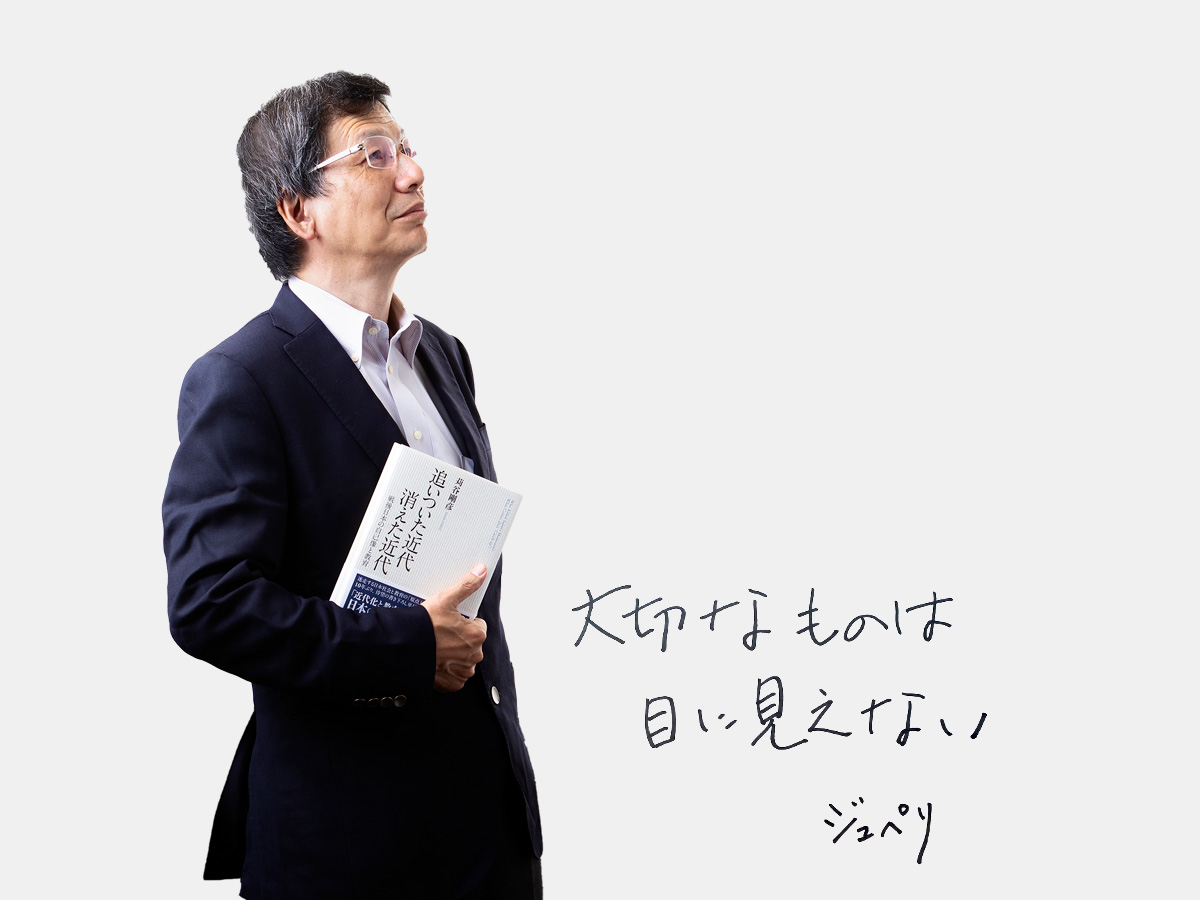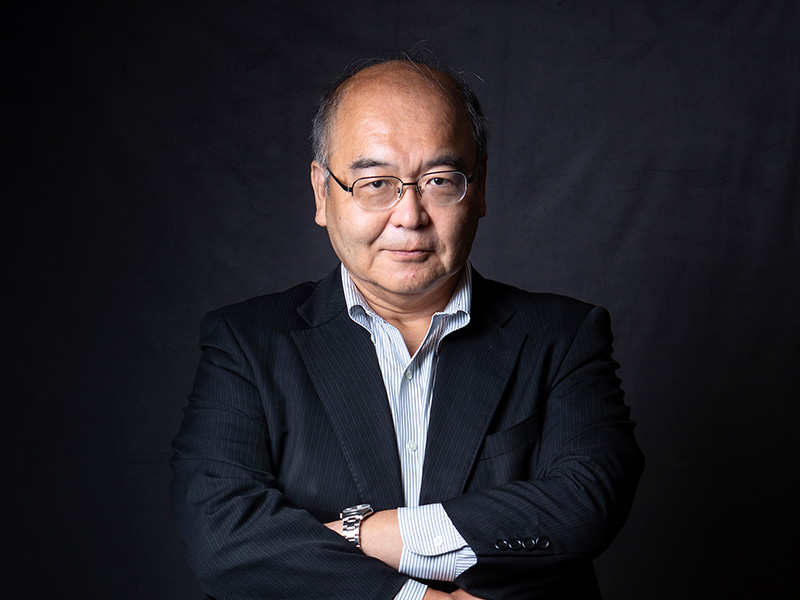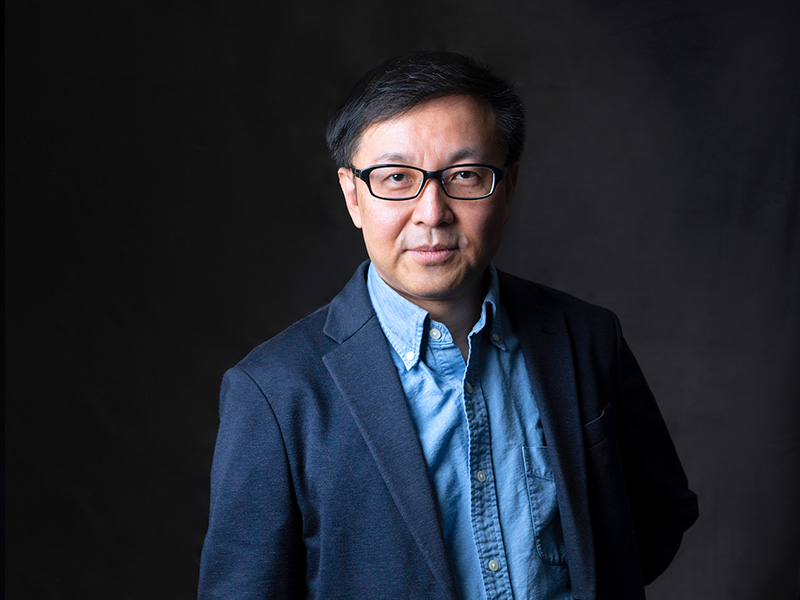博士(学術)
AkiraNakamura
中村明
変化に適応し、新たな機会の獲得を!
- 専任教授(研究者教員)
- 八千代エンジニヤリング株式会社事業統括本部海外事業部 顧問・統括技師長
- 神戸大学非常勤講師(国際関係論)
- 国際P2M学会副会長、理事
- 土木学会、国際P2M学会、アジア交通学会、化学工学会の会員
- 中学・高校でのSDGs・探究活動、自治体が中心となる地域の企業のSDGs推進に関与
Question
担当している領域・科目について教えてください。
ミッション達成型事業マネジメント概論、ミッション達成型事業マネジメント実践化演習、中小企業プログラム立案ケーススタディ、経営戦略という4つの科目を担当しています。
プログラムとは、複数の有機的につながりのあるプロジェクト群から構成され、プロジェクトよりも上位の目標の達成を目指す枠組みです。現在社会に存在する課題は、多種多様で、かつ複雑化しています。その中で従来のプロジェクトマネジメントという枠組みだけでは、目的を達成することが難しくなってきたことから、2000年ぐらいから世界でプログラムマネジメントいう考え方が広がりました。当大学院においては、プログラムという枠組みとプログラムマネジメントの社会課題解決や企業価値向上への適用に関する授業を担当しています。現代社会は、あらゆる面で日々変化する状況にあり、変化への対応が、生き残るために必須の課題であると考えられます。そのためには、現状を読み取り、未来に向け、あるべき姿、ありたい姿を描き、その取り組みを実践化していくことが重要であると考えられます。担当する科目では、社会の動向、技術の動向、そして企業、個人がどうあるべきか、を考えながら、複雑な課題の解決や新しい価値創造をどのような道筋で、どのようにマネジメントして、達成するのか、というテーマに取り組みます。
アイデアを発散的に洗い出し整理収束するための考え方、ロジックモデル、システム思考、デザイン思考、アート思考、行動経済学などを方法論として活用します。また、EBPM(Evidence Based Policy Making)の考え方を重視し、データに基づき、人文社会科学を考えるアプローチを取ります。授業を通じ、技術の価値をどのように引き出すのか、SDGsやPRI/ESG投資など、昨今話題となっている動きをどのように理解し、それにどのように対処すれば良いのか、という点についても答えを出していきます。
実務家時代にどのような業務に携わってきましたか?
社会人としての最初の出発点は、橋梁エンジニアでした。吊橋、斜張橋と呼ばれる、スパンの長い特殊橋梁の耐震、耐風、疲労などの解析・設計に従事しました。技術とは何か、エンジニアの役割とは何か、といった点について様々な経験を通じ、考える機会となりました。1981年にアメリカで出版された「America in Ruins(荒廃するアメリカ)」という書籍がエンジニアとしての自分の考え方を大きく変化する転機となりました。今まで目標としてきたアメリカの歴史的橋梁が通行止め、落橋の危機に瀕しているとの事実を知り、構造物、インフラは建設するまでの技術だけでなく、完成後、人間の命のように健康に維持していくための仕組みが重要であることを認識しました。
もともと途上国問題に関心があったことから、キャリアの多くをJICAという組織で過ごし、途上国の開発プロジェクトに従事しました。途上国の直面する多くの社会課題に取り組み、改めて技術とは何か、社会課題を解決するために必要な要素とは何か、そのアプローチはどうあるべきかかということについて、試行錯誤する機会となりました。個々の要素的技術に加え、その技術を社会に生かすための技術、いわば専門技術を社会に橋渡す技術の重要性を知りました。
以上の経験を経て、現在自分自身が担当するプログラムマネジメント、社会課題解決へのアプローチなどの担当する科目の授業内容が出来ています。
直近の6年間は大学教育に従事し、今までの実務家としての経験を整理・体系化しつつ、教鞭を取っています。目標とするところは、社会に役立つ、実践に適用可能な教育の実現にあります。講義という形でクラスに問題提起を行いしつつ、クラスの方々と共に学び、新しい知を築くことを目指しています。
授業を行う際に大切にしている点は何でしょうか?
大学院の授業は、教員だけでは決して作れないものだと考えています。リカレント教育に相応しい素材をクラスに参加された方々に提供するとともに、共に考え、学び合うことが重要であると考えています。科目によって、授業の方法や素材は、異なる面はありますが、受講者の皆さんに新しい気づきを与え、参加者の皆さんの考えや知見も引き出し、それにより活力のあるクラスが実現するよう努力しています。
また、特定課題研究のゼミでは、特定課題研究を取りまとめるということに加え、大学院ならではの知性を磨けるよう今まであまり考えてみなかったことなどを一緒に考えていく、創造的な場にすることを目指しています。
Information
スチューデントアワー
春学期:土曜日 9時30分~11時00分
夏学期:土曜日 9時30分~11時00分
秋学期:土曜日 9時30分~11時00分
冬学期:土曜日 9時30分~11時00分
対面、もしくはオンラインで対応しますが、授業などで時間が合わない場合は、メールにてアポのご連絡を頂ければ、時間の調整をします。
専門分野
プログラムマネジメント、ステークホルダーマネジメント、現状分析、社会調査、社会課題解決、SDGs、ESG投資、インパクト評価など
分野としては、地域活性化、観光開発、インフラ開発、都市・地域開発、ジェンダー平等/多様性、防災、開発マネジメント、サステナビリティ、組織改革、人財育成、新しい価値の創造、海外展開など
現職と主たる経歴
- 10年ほど、建設コンサルタントにて、構造物の計画・設計・解析などに従事。レインボーブリッジ、明石海峡大橋、来島海峡大橋などの耐震・耐風設計に従事
- JICA(国際協力機構)にて、開発援助プロジェクトの調査・企画、実施、制度設計、フォロー、評価、人材育成などに従事。専門は、インフラ開発、都市・地域開発、平和構築、ジェンダー、災害復興、開発マネジメントなど。社会基盤・平和構築部長、経済基盤開発部長、国際緊急援助隊事務局長、企画部次長など。
- 関西学院大学国際教育・協力センター教授としてグローバル教育に従事。グローバル関連科目、海外フィールドワークなどに取り組む。
- 2000年初頭にJICA内でP2M(Project&Program Management)研究をスタートし、現在まで約20年間、プログラムマネジメントによる社会課題の解決、組織での価値創造などを研究フィールドにする。
- 東京農工大学工学府博士後期課程修了応用化学専攻(博士(学術))、技術経営修士(MOT)、工学士(土木工学)
《現職》
・日本工業大学大学院 技術経営研究科 専任教授
《学位》
・博士
《経歴》
2017.4~2019.3 関西学院大学 国際教育・協力センター 教授
世界市民論、国際情報分析、グローバルゼミ、開発、国際平和構築論、海外フィールドワークなど
2018.6~2018.8 神戸大学非常勤講師
国際関係論
1993.4~2017.3 国際協力機構(社会基盤・平和構築部長、国際緊急援助隊事務局長、企画部次長、資金協力支援部審議役、社会開発部次長、社会開発調査部、無償資金協力部、フィリピン事務所など)
政府開発援助の一環として実施する技術協力及び資金協力に関連するプログラム及びプロジェクトの企画、調査、計画、実施管理、フォローアップ、評価、制度設計、予算管理、調査研究など。分野としては、都市開発、地域開発、運輸交通・情報通信関連のインフラ開発、ジェンダー平等・貧困削減、災害復興、平和構築、農業開発、プログラム&プロジェクトマネジメントなど。
1983.4~1993.3 建設コンサルタント
橋梁計画・設計・解析など
その他
《博士論文》
持続可能な社会形成のためのプログラムマネジメント適用化に関する研究
ODA事業における全体最適化と価値システムについての考察
開発途上国における開発計画策定支援の意義とその実行へのPPP適用に関する研究
グローバル化する災害復興支援におけるPM体系の役割について
日本の国際緊急援助隊におけるプラットフォーム形成
持続可能な社会形成のためのキャパシティディベロップメント適用化に関する研究
開発プログラムにおけるジェンダー平等の視点に関する考察
多様性とマネジメント
フィリピン国台風ハイヤン被災地での国際緊急援助隊医療チームの活動報告~平時の準備がもたらした成果に焦点をあてて~
ODA事業におけるプログラムマネジメント
Future Perspectives and Challenges for Realizing Sustainable Societies– in terms of program management –
開発途上国におけるインフラ開発の現状と課題
JICAにおける持続可能な開発への取リ組み~プログラムマネジメントの視点から~
《受賞実績》
2009年5月 土木学会国際活動奨励賞受賞
《備考》
所属学会 国際P2M学会、土木学会、化学工学会、アジア交通学会